■中小企業:経営ビジョンと事業計画が欠落
中小企業庁の発表(平成14年4月)によれば、平成13年の中小企業の倒産件数は史上3番目の高水準で、特に老舗企業の倒産が増加しています。
このように経営環境や業績が悪化しているにもかかわらず、多くの中小企業においては、経営体質の改善について問題を先送りしているところが少なくありません。
いま、そこをどう打開してゆくのかが最大の課題となってきています。健全な経営を実現する為には、経営ビジョンと事業計画の策定が不可欠です。しかし、これまで「なりゆき経営」を続けてきた中小企業の場合は、そのような理想的なレベルにまで一気に到達することはきわめて困難です。
このように経営環境や業績が悪化しているにもかかわらず、多くの中小企業においては、経営体質の改善について問題を先送りしているところが少なくありません。
いま、そこをどう打開してゆくのかが最大の課題となってきています。健全な経営を実現する為には、経営ビジョンと事業計画の策定が不可欠です。しかし、これまで「なりゆき経営」を続けてきた中小企業の場合は、そのような理想的なレベルにまで一気に到達することはきわめて困難です。
■まず、今期の「決算対策」から始めよう
私たちは、その最初のステップとして、まず「継続MAS」利用による今期の決算対策から着手することを提案しています。いまや赤字決算を続けることは命取りになりかねません。期末までに残された期間内で、どれだけ業績を改善できるのかを検討しようということです。検討の結果、今期は赤字決算が避けられない場合であっても、来期には黒字決算とするための布石を考える事になります。
そのような業績検討会を経営者と経営幹部の同席の下に継続することにより、「気づき」と「やる気」が醸成され、経営ビジョンも徐々に明確なものとなってきます。
そのような業績検討会を経営者と経営幹部の同席の下に継続することにより、「気づき」と「やる気」が醸成され、経営ビジョンも徐々に明確なものとなってきます。
■事業計画は「経営者への5つの質問」から
事業計画の作成は、当期の決算予想額を確定したあと、経営者に対する次の5つの質問からスタートします。
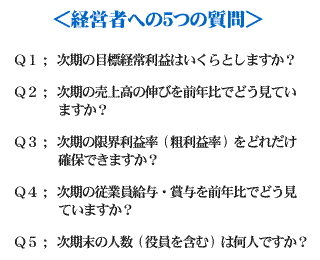
これらの質問から、次期の事業計画の骨格を作ることができます。これに加えて、詳細な事業計画を練る場合は、設備投資計画、資金繰り計画、部門別利益計画等に関する質問が「ツール・ボックス」に用意されています。
また、このようなシミュレーションを将来3年間にわたって続けることができます。
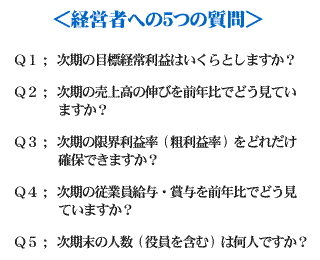
これらの質問から、次期の事業計画の骨格を作ることができます。これに加えて、詳細な事業計画を練る場合は、設備投資計画、資金繰り計画、部門別利益計画等に関する質問が「ツール・ボックス」に用意されています。
また、このようなシミュレーションを将来3年間にわたって続けることができます。
■首尾一貫した事業計画書の作成
この「継続MAS」から作成される各種の報告書は、将来計画を含めて、単一のデータを基礎としたものです。したがって過去の財務データとの継続性の保証はもちろん、資産、負債、資本、収益、費用取引の相互関連及び法人税と消費税の税額計算についても、首尾一貫した内容のものになっています。
①「戦略的決算対策報告書」 →サンプル表示
決算期の3か月前までに作成します。
②「経営計画書」 →サンプル表示
新しい事業年度の始めに作成します。
③「業績検討会報告書」 →サンプル表示
四半期ごとに作成します。
④「企業格付自己診断表」 →サンプル表示
決算終了直後に作成します。
①「戦略的決算対策報告書」 →サンプル表示
決算期の3か月前までに作成します。
②「経営計画書」 →サンプル表示
新しい事業年度の始めに作成します。
③「業績検討会報告書」 →サンプル表示
四半期ごとに作成します。
④「企業格付自己診断表」 →サンプル表示
決算終了直後に作成します。